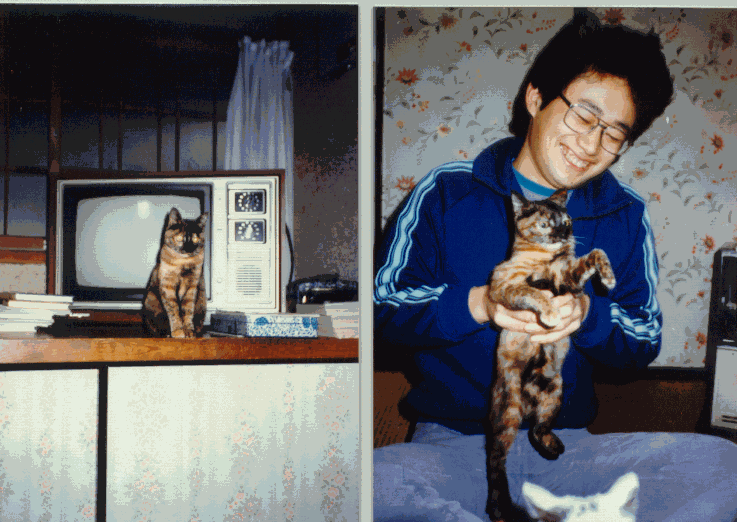猫
わたくし、猫でございます。 名前を『もぐ』と申します。
兄弟三匹といっしょに捨てられて、一日中どしや隆りの雨の中で泣いておりました。夜になってコンプレッサー小屋で雨を避けていたところを、ご主人様と奥様が壊中電灯を持って捜しに来てくださいまして、私だけが拾い上げていただきました。
湯沸かし機の暖かいお湯で洗っていただき、タオルで赤ちやんのように包んでいただきました。お皿にいただいたミルクを自分では飲むこともできず、スポイトで口の中に注ぎ込んでいただいたときには文字通り生き返る思いでございました。
その時には目も明けられなかったのに、あまりの心地よさとおいしさに思わず喉を鳴らしたのでございます。 奥様は、
「まあっ、喉を鳴らしているっ。こんなに小さいのに、目も開かないのにっ」
と、大変感動なさって、その時から私はこの家の家族になったのでございます。
それはもう十六年も昔のことでございました。
私の毛並みは黒と茶と黄色の複雑な縞模様で、ご主人様は床板の色と紛らわしくて踏みそうになとるおっしやいます。実際、踏まれたり蹴飛ばされたりしたことが何度もございましたが、この毛並みのせいでございましょうか。
私の名前は奥様のところに、お習字とやらを習いに来たこどもたちが、
「もぐらのような猫だ」
と、言ったところからついたのでございます。
さて『信濃の民話』というご本に、和尚様に愛されたご恩返しに、新しい檀家をお世話した、偉い猫の話が載っているそうでございます。
何百年も昔のお話なのにそのお寺では、猫がお世話した檀家を今もなお、猫檀家と呼んでいるそうでございます。
詳しいお話は図書館においでになって、そのご本をお読みくださいませ。
ご主人様のお母様の生家はその猫檀家だそうで、人間界では幅のきかないご主人様も、私ども猫の飼い主としては大変良いお毛並みなのでございます。
それなのに、私が拾われたときのご主人様のお言葉は、
「猫の子が捨ててあったなんて、言わなきや良かった。また猫が一匹増えた」
と、いう冷たいものでございました。
『また一匹』と申しますのは、わたくしが拾われる前から『ミー』という雌猫が飼われていたからでございます。
このミーと申します猫は、初めは私を避けていたのでございますが、わたくしが母恋しさに近寄りますと、前足で私を転がして遊ぶようになりました。
逃げられても、転がされても私という猫はあきらめることを知りません。
幾日かたってミーは私を舐めてくれるようになりました。
体中くまなく舐めてくれまして私が、
「ミーミー」
と、甘えますと、本当にかわいがってくれるようになりました。
ご主人様は、
「これが本当の猫っかわいがりだ」
と、お笑いになりましたが、目も開かないうちに捨てられた私にとって、本当に幸せなことでごさいました。
すっかり元気になったわたくしはある朝、ご主人様が棚の上のものを取ろうとして伸びあがった時に、そのかかとの下に入ってしまったのでございます。
ご主人様に踏みつけられて、頭の骨が、
「がりっ」
と、音を立てたのを微かに覚えておりますが、そのまま激痛のために気を失ったのでございます。
気がついたのはビニール袋の中でございました。
ご主人様は私が死んだものと思い、庭先に埋葬の用意をしておられました。
私の泣き声に気づかれた奥様に助け出されてからも、あまりの激痛にただ寝ているばかりでございました。
ミーの献身的な看護のおかげで少しづつ動けるようになりましたのは、五日もたってからでごさいました。
十日ほどたってから、あっちへよろよろ、こっちへよろよろと、よろめきながらも歩くことができるようになったのでございます
わたくしの歩き方をご覧になってご主人様は、
「命冥加なちび猫め」
と、お笑いになるのでございました。
あんまりではございませんか。ご自分にも責任はおありなのに。
しかし、ごく気紛れに、ご主人様にあぐらの上に乗せて体をなで回していただいたときには、それは良い気持ちでうっとりとしてしまい、自然に喉が鳴ってしまうのでございました。
あぐらの上が大好きになったわたくしは、ご主人様がお座りになるのを見るとすぐに駆け寄り、膝によじ上るようになりました。
「猫なんか好きじやないよ」
と、つれないことを言いながら、押し退けられても払いのけられても、決してあきらめず幕い寄る私にご主人様は、
「こう募われては、嫌いだなんて言ってられないな」
とおつしやって、
『やすらえば猫募い寄る夜寒かな』
と、いう俳句を作って句会にお出しになりましたが、人間のお仲間は誰も喉を鳴らしてはくださらなかったらしうございます。
ミーにはよくしてもらいましたが、それも一年ほどでございました。ミーはかわいそうに、人間が乗り回す自動車と言うものにひき殺されてしまいました。
人間は大きな足をお持ちなのに、どうしてあんなものに乗らなければならないのでございましょうねえ。
ミーが死んで間も無く、ご主人様のご都合で別の家に転居いたしました。
私ども猫と申しますものには、新しい環境が怖いのでございます。いくにちも動けないでいる私にご主人様は、
「借りてきたようだなあ」
と、お笑いになりました。
こんなときでも人間は冗談が言えるのですねえ。
すっかりこの家に慣れた頃のこと、私は外に出てみたくなりました。
戸口でニヤーニヤーと奥様にせがみましたが、
「危ないから駄目」
と、出してくれません。
しかしわたくしはあきらめることを知らない猫でございます。いつまでも喚いておりますと奥様は、癇癪を起こされて、(奥様は見かけによらず癇癪持ちなのでございます)
「そんなに出ていきたいのなら行きなさい。もう帰ってこなくても良いから」
と、おっしやって戸を開けてくださいました。
そんなことを言われても、生まれつきの野良でさえ生きにくい野良猫社会に、私が適応できるはずがないでわありませんか。
私は戸口から外を見るだけであきらめることにしました。
それをご覧になってご主人様と奥様は大笑いされました。
ある日、ご主人様が書き損じた伝票を丸めている音を聞きまして、あれにじゃれてみたいと思い、身構えました。
ご主人様はそれを私のほうへ投げてくださいました。私はさっと飛び上がって宙で受けると、前脚で転がしながら部屋中を駆け回りました。
ご主人様はそれをご覧になって、
「サッカーのドリブルのようだ」
と、感心なさいました。
この紙つぶてはボールのように転がりすぎず、わたくしが遊ぶのにこれほど良いものはあるまいと思われます。ドリブルだけではなく、ご主人様が謡曲を謡うときにおしりの下に入れる座椅子の脚の間を転がして通したり、いろいろな遊びができます。それにいたしましてもあの謡曲の声というものは、恋猫でも恥ずかしくなるようなすごいものでございます。
一つの遊びに飽きて違う遊びをしようと、紙つぶてをくわえて歩きますと、ご主人様も奥様もなぜか楽しそうに、喉を鳴らして喜ばれます。
私が得意気に腰をひねって歩きますと、
「ちびめ、虎になったつもりだ」
と、ますます喜ばれます。この家に慣れてからというものは、苦手な客は減多に来ませんし、お二人にかわいがられて幸せな日を送っておりますが、一年に一回だけは本当に怖い思いをするときがございます。
わたくしどもが住んでおります家の前に町の公民館がございまして、さほど広くもない庭に、予防注射のために犬が集められるのでございます。
たくさんの犬が集められ、あのどう猛な声と獣臭い匂いがしてきますと、ご主人様に抱かれていても奥様の膝にいても、震えが止まらないのでございます。そんなときは押入の奥深く潜り込んで、犬のいなくなるのをじいっと待っているのでございます。
押入のからかみや障子を開けることはずいぶん前からできました。ようやく戸を開けられるようになったとき、たまたま帰省しておられたぼっちやまが、
「猫も戸を開けられるようになれば一人前だな。後を閉めるようになれば化け猫だ」
と、おっしやいました。
後を閉めるということがどんなことか、私にはわかりませんが、たとえわかっても、それだけは決してすまいと思っています。
さきごろ、
「長生きしたなおまえ。もう十六歳だぞ」
と、ご主人様がおっしやいました。
「二十三年も生きた猫がいたんですって。しまいには惚けてしまって、おしめを当てるようになるそうよ」
と、奥様がおっしやいますと、
「冗談じやない。これだけ家族になり切ったものを、保健所に持っていくわけにもいかないし」
と、ご主人様も心配そうでございます。
わたくしにしてみれば、それこそ冗談ではごさいません。紙つぶてにじやれ、カーテンにぶら下がり、柱に駆け上がり、障子をぶち破り、仔猫のままの十六歳でございますよ。
このわたくしが惚けるなんて、そんな心配をなさるから、お二人ともこのごろ白髪が増えたのでございます。
今夜もご主人様は私を膝に乗せてくださって、
「おい、婆猫」
と、おっしやいながら、
『胡座に丸き猫のいびきや秋長し」
と、一句ものされたのでございますが、失礼な、わたくしはいびきなどはかきません。
この分ではご主人様の俳句は、とてもものにはなりますまい。
俳句は駄目でも、そんなことは私には関係ございません。ご主人様のあぐらの中にすっぽりとはまりこんでおりますと、この世の極楽でございます。
「コロゴロ、ゴーロゴロ」
いえ、いびきではごさいません。こう気持ちがよいとつい喉が鳴ってしまうのでございます。気持ちが良くて、これ以上お話を続ける気にはなれません。
お休みなさいませ。
「ゴーロゴロ」 平成9年
猫の死
12月の初めころ、飼い猫「もぐ」が元気をなくして高い所へは上らないし、走り回ることもなくなってきた。
年のせいかなと思っていると、今度はえさを食べない。妻もわたしも不審には思ったものの、年のせいかぐらいに軽く考えていた。
2・3日して妻が獣医に見せたところ、
「歯が悪くてものが食べられなかった。脱水症状になっている」
ということで、化膿止めと栄養剤の注射をしてもらってきた。
ようすを見ていたがその翌日もえさを食べなかった。翌々日、日曜だったが獣医がいれば見てもらえるかもしれないと、妻が抱いていったのだが獣医は留守だった。あまりに具合が悪そうだったので私が薬局で抗生物質を買って来て、5ccくらい入るスポイトで水といっしょに口に流し込んでやった。喉を通る時、猫は痙攣を起こして、体を反らせ硬直して私の手につめを立ててしがみついた。
「しまった、このまま死んでしまうか」 と、思ったがその時は1分くらいで収まった。ときどき家の中を歩き回るのだが、歩幅が狭くなり弱りきっているのがわかる。
「もうだめね」
妻はタオルに包んだ「もぐ」を抱いて泣いた。「もぐ」はタオルに包まれるのが大好きで盛大に喉をならすのが常なのだが
、その時にはただじっと目を細めているだけだった。
翌日の未明妻が見たときには、「もぐ」は死んで硬直していた。
平成9年12月15日であった。16年前夏の激しい雨の日、工場の脇のごみの中で猫の鳴き声のしていたのは知っていたのだが、拾う気もしなかった。夜になってうっかり妻に話すと、懐中電灯を持って雨の中を探しに行くと言う。しかたがないのでついて行ったが猫の姿は見当たらなかった。
諦めきれない妻が工場の並びのコンプレッサー小屋を覗くと私の拳よりも小さい猫がうずくまっていた。
拾ってかえり、湯沸かし器の湯で洗うと白い小さな蛆が黒っぽい毛の間から出てくる出てくる、際限もないありさまであった。
タオルに包んで抱くと言うよりは手のひらに乗せて、拭いている間にもまだ蛆が湧くようにででくる。
ようやく一段落して、皿にミルクを入れて与えたのだが、飲むこともできなかった。しかたがないのでまたタオルで包んで妻がスポイ
トで口の中に注ぎ込んでやった。
2・3回つぎ込んでやると、
「グツッ」
と、言う。妻が耳を寄せると喉を鳴らしているようだ。
「まあ! 喉を鳴らしている!」
妻は感動した。
「こんなに小さいのに! 目も明かないのに!」
妻は涙をこぼさんばかりに感動した。
一人息子を大学へ出してやった年であった。
その子がまだ幼かったころ、道ばたに捨てられていた小猫を拾いたがったのを妻が拒んだことがあったという。
翌日妻は、
「お母さんが助けてやらなかったから小猫が死んでいた」
と言って、子に泣かれたのを思い出して、助けてやろうとしたのであった。
子の出ていった後の寂しさは妻だけのものではない。
この時拾った猫「もぐ」が16年の間その寂しさを、どれだけ慰めくれたかしれない。
「もぐ」は一度子を生んだが、その子猫は育たなかった。その後不妊手術をした。
手術をしたためか、あまり大きくならず、おとなになりきらないようで、甘えたりじゃれたりしていた。
いまでも妻は寝ているとき布団の隅に「もぐ」がいるようだという。
先日、妻が用事で朝早くに外出して私が一人で春眠を貪っていると、隣の部屋で「もぐ」が畳の 上を「さささっ」と走りまわる気配がする。
首を上げて見ると妻の癖で障子をもぐの通れるくらい開けてあった。
生きていたとき「もぐ」は走り回るのに飽きると、細く開いた障子の間から「とことこ」と小さな足音たてて入って来て、私が布団から手を出していると小指の外側を歯を立てないようにそっと噛んで起こそうとしたものだつた。
知らぬふりをしていると冷たい鼻を私の頬に押し付けてくる。
そのときは聞き耳を立てていたのだが、音はせず気配だけが確かに感じられた。布団から手を出して待っていたが、それっきりだった。後で妻に話すと、
「葬式もしてやらなかったから、成仏できないのかしら」
と言う。
「葬式と言っても、猫の耳に念仏じゃ、しゃれにもならないよ。葬式なんて残された人のためのもので、死んだ本人には何の意味もないよ」
と、私が言っても妻には釈然とできない何かが残るようである。
「あいつは『恨めしや』って出でくる奴じゃないよ。『もっと遊びたいよ』なら分かるけどね」
「そうね」
妻は笑い出しながら、
「もう二度と猫は飼わないわ。人と猫にも相性があるものね。あんな猫にもう二度と逢えないから」 と、言う。
寂しくなった。 平成10年4月30日